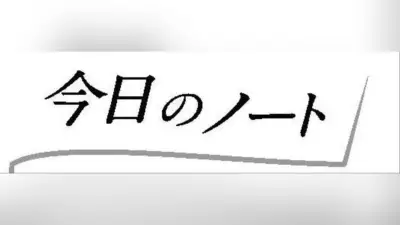震災犠牲者の名を刻むことの重み
並んだ名前を見つめていると、まるで子どもの頃に戻ったような感覚に包まれる。世話好きだった父、墓地のお供え物を一緒につまみ食いした親友、それを見て優しく笑っていた和尚さん、放課後に「腹減ったべ?」とおやつをくれた近所のおばちゃん、夏の肝試しを見守ってくれたおじちゃん――。
彼らは皆、東日本大震災によって尊い命を落とした。その一人一人の名前が、今、岩手県大槌町の追悼施設「鎮魂の森」に刻まれている。
「鎮魂の森」に刻まれる1272の名前
海に向かって立つ幅20メートルほどの石碑には、犠牲となった町民一人一人の名が15センチの銘板に刻まれ、丁寧にはめ込まれている。その数は1272人に及ぶ。
岩間敬子さん(63)はこの施設を訪れるたび、父・伊藤勝一郎さん(当時77)の名前、そして近所の人たちの名前をじっと見つめ続ける。「それぞれの名前の上に、その人との思い出が浮かんでくるんです……」と語る彼女の目には、自然と涙がにじむ。
父は津波にさらわれ、今も行方が分かっていない。「何年か前だったら、名前を刻むことに抵抗があったかもしれない」と岩間さんは振り返る。
名前が語る一人一人の物語
被災地のガイドも務める岩間さんは、今年1月9日、町外から訪れた会社員3人に対して、銘板の前でこう語りかけた。「人口の1割の町民が犠牲になりました。でも、数字だけで聞き流さないでほしい。これだけの人が、一人一人いなくなったんです」。
慰霊碑に並ぶ震災犠牲者の銘板の前で、町外から訪れた人々に語りかける岩間さんの姿は、名前を刻むことの意義を静かに伝えている。
名を記すことへの複雑な思い
しかし、すべての犠牲者の名前が刻まれているわけではない。東日本大震災で犠牲になった2万2千人を超える人々には、一人一人に固有の名前がある。被災地では、その名を刻むことが「生きた証し」や「心のよりどころ」になるとの声がある一方で、「見せ物ではない」という訴えも聞かれる。
名を記すか、記さないか。この問いは、震災から15年が経過した今も、遺族や関係者の間で深く考え続けられている。
時間がもたらす変化
岩間さんは「時間の経過とともに、名前を刻むことへの思いも変わってきた」と語る。当初は生々しすぎると感じていたかもしれないが、今では父や近所の人たちの名前が刻まれていることに、ある種の安らぎを見出しているという。
「それぞれの名前が、それぞれの人生を語っている。それは単なる記号ではなく、その人が確かにここにいた証なのです」と彼女は静かに続ける。
未来への継承
震災の記憶が風化しつつある今、犠牲者の名前を刻むことは、単なる追悼を超えた意味を持つ。それは歴史の証言者としての役割を果たし、未来の世代に震災の実相を伝える重要な手段となっている。
「鎮魂の森」に刻まれた1272の名前は、単なるリストではなく、それぞれが豊かな人生を送った人々の生きた証しとして、静かに海を見つめ続けている。